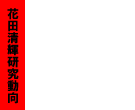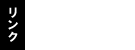「光源としての唯物論的ユーモア―尾崎翠と花田清輝6/10

実生活における敗北とテクストは等価でなければならないという川村の思い込みを裏切るかのように、このテクストのディスクールは、花田が「異常なまでにあかるい日のひかりのみちあふれたようなその小説」と形容したような不思議な効果をもたらしているのである。その一端は花田ではなく皮肉にも、花田のエッセイによって尾崎翠に導かれた山田稔によってあきらかにされてきた。
山田は、「第七官界彷徨」のディスクールの効果の特徴をユーモアにみ、「一方には『哀感』があり、他方には『滑稽』がある。しかしそのいずれもが単一の感情として表現されるのではなく、つねに他の異質の感情、たいていはそれと対立する感情と組み合わされて示される
」とする。たしかに、それはテクストに遍在する愛、すなわち一助の患者への恋、二助の失恋と植物への恋、三五郎の町子と隣人の国文科聴講生への恋、そして、町子の三五郎と柳浩六への恋の場面においてあらわれている。たとえば、<私>が「哀愁」をまぎらわそうと口笛を吹くと、それは三五郎には「心の愉しいしるし」としてとどき、彼は自分の部屋から<私>のコミックオペラに侘びしい音程をもったピアノの伴奏と彼自身の声楽を送ってよこす。するとその音楽は失恋の傷を深く心に秘め、蘚の恋愛の研究に没頭している二助の歌を喚起する。
二助のコミックオペラは家つきの古ピアノの幾倍にも侘びしく音程が狂い、葬送曲にも似た哀しさを湛えていたのである。しかし、二助はなかなか愉しそうな心で歌いつづけた
。 このような<哀感>と<愉しさ>といった対立的な感情の複合ばかりでなく、異なる感覚も複合される。 ……三五郎のピアノは何と哀しい音をたてるのであろう。年をとったピアノは半音ばかりでできたような影のうすい歌をうたい、ちょうど粘土のスタンドのあかりで詩をかいている私の哀感をそそった。その時二助の部屋から流れてくる淡いこやしの臭いは、ピアノの哀しさをひとしお哀しくした。そして音楽と臭気とは私に思わせた。第七官というのは、二つ以上の感覚がかさなっってよびおこすこの哀感ではないか。そして私は哀感をこめた詩をかいたのである
。
こうした<悲しみ>と<滑稽>という対立する感情、聴覚と嗅覚を複合するディスクールの方法として、山田は映画の「モンタージュ」をみ、狩野啓子は、音楽の「対位法」を読み取っている
。山田が指摘するように「映画のモンタージュはまず視覚的イメージの間で成立し、トーキー時代に入って音の要素が加わると、エイゼンシュテインのいわゆる『視覚像と聴覚像との交響学的対位法』となって発達
」する。
エイゼンシュテインの生涯のライバルであったプドフキンは、モンタージュをショットとショットのリンケイジと理解していたが、エイゼンシュテイン自身にとってそれはショットとショットの衝突であり、その葛藤であった。彼にとってモンタージュは衝突である以上、あの名作『戦艦ポチョムキン』の視覚イメージのモンタージュがもたらす統一性は完璧すぎてむしろこの方法のもつ可能性から遠ざかるものではないかという不満を彼に抱かせたのである。エイゼンシュテインは、ドイツでの『戦艦ポチョムキン』上映に際してエドムンド・マイゼルに無音調で刻まれたリズムの音楽を要求し、映像と音楽との対位法の成立をめざした。そうした彼にとってトーキイ映画の可能性は、「視覚的な映像と音との鋭い不一致という方向
」にあったのである。
尾崎翠がモンタージュを学んだのはエイゼンシュテインではなく、サイレント映画のチャップリンであったが、彼女はそこにエイゼンシュテインによって正統的に受け継がれる視覚イメージの「鋭い不一致」の方法とそこから生まれるユーモアとペーソスを学び、物象化された「もの」への偏執、たとえば「杖」と「帽子」に共感を覚えたことは「映画漫想」に詳しく記されているとおりである。彼女はそれらを「第七官界彷徨」のなかに取り込んだ。おかしな人々の愛を物語るために。