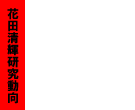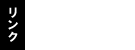花田清輝の研究動向
菅本康之
去年の秋、久保覚が息をひきとった。おそらく、全共闘以後の世代で久保の名を知るものは少ないだろう。彼の人生の後半は、必ずしも輝いたものではなかった。むしろ、彼自身の才能からすれば、痛ましいものであったとさえいえる。流行それ自体が物心崇拝の対象となってしまう現代の日本の状況は、彼がいきいきと活動できる場を著しくせばめていったのである。
久保覚は、現代思潮社の、たぐいまれな編集者として六〇年代を生き、高良留美子の言葉を借りれば、吉本隆明や谷川雁、花田清輝や埴谷雄高と読者との間を媒介しながら、「否定性」の文化をつくりあげていった。もちろん、90年代のポストモダニストには、こうした文化は古色蒼然たるものに見える。だが、そうしたポストモダニストでさえ実は知らず知らずのうちに彼の恩恵を受けてきたのだ。なにしろ久保はあのミハイル・バフチンの「ラブレー論」を日本に紹介した編集者なのだから。
彼はバフチンのテクストに出会ったとき「バフチーンの問題意識が花田清輝ときわめて似ていること」に衝撃を受ける。「バフチーンも、カーニバル文化というまさしく活字以前の民衆文化を洗いだすことによって、これまでの個的な次元にしばりつけられた活字文化的ラブレー解釈をうちくだいていた。……バフチーンの視点と重なりあう花田清輝の視聴覚文化論は、日本の文学と思想の現状にたいする批判を中心にして、過去のなかに眠っている可能性をつかみだし、それを未来を指向する力へと変貌させていく作業にほかならなかった。」このように述べる久保の仕事の頂点をなすのはいうまでもなく『花田清輝全集』(講談社)の編纂であった。この『花田清輝全集』(一九八〇年完結)によってはじめて「やっかいな芸術家」花田清輝の足跡がすべて検証できるようになったのである。
だが、彼が渾身の力を傾けた仕事であるにもかかわらず、バフチンのブームが欧米を席巻したようには、花田清輝ルネッサンスは日本に訪れなかった。花田没後十年に際し、久覚は苛立ちを込めてある新聞に次のように書く。「いわゆる大手のどの論壇・文芸ジャーナリズムも、その没後十周年にさいして、まったく一言さえも費やそうとはしなかった
。」その流れに抗して、久保は『新日本文学』の編集長として花田清輝の全頁特集を企画する(一九八四年一二月号)が、これは久保が花田に関わった最後の仕事となったと同時に、いままでのところ雑誌メディアにおける最後の花田特集となってしまっている。久保の晩年の不遇は、まさに花田が黙殺されていくのと相同的であったのである。そうした状況のなかで「花田清輝の研究動向」というテーマは、おそろしくアイロニカルだが、まずは花田の可能性を提起しつづけた久保への追悼からはじめねばならない。
花田の黙殺・忘却に抗する仕事は、かろうじてではあるが現在まで紡ぎだされてきた。ここではそうした仕事に焦点を合わせる。具体的には、『全集』刊行以後から現在までのおよそ二〇年の期間のものを対象としたい。『全集』刊行以前にも優れた仕事は少なからずあるが、久保を追悼し、忘却に抗するという観点から『全集』刊行をひとつの分岐点とする。