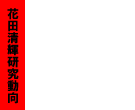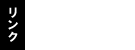花田清輝の研究動向2/4

花田の忘却は、彼が戦後期の唯一もっとも重要なマルクス主義批評家であったことと深く関わる。日本の革命運動が停滞し、やがて瀕死の状態にまで追いこまれていくプロセスと、彼の黙殺・忘却は照応しているのである。それゆえ、花田と歩みをともにしたひとびとは、切実な痛切な思いをもってその流れに抗し、革命運動を生きつづけた花田を想起する。関根弘による『花田清輝 二十世紀の孤独者』(リブロポート)は、現在のところ信頼に足る唯一の花田の評伝である。(関根はこの書の数年後、痛ましい自死をする。)武井昭夫と湯地朝雄は、多くの同士がこの世を去り、生き残ったものの少なからずが変節していくなか、これまでの運動の伝統を守りつづける。湯地は難解といわれる花田の『復興期の精神』を時代背景のなかで読み解いていき(「『復興期の精神』の思想とその背景」)、武井は花田の生きた運動と時代を照らしだす(「芸術運動家としての花田清輝」)。(『社会評論』、NO106、110)老いてなお彼らは精力的だが、問題なのは、彼らの後継者が運動のなかから生まれていないことだ。運動が敗北したわけでないにしても、退却戦を余儀なくされている現状では、危急の課題は若い世代に、とくに花田の死後に生まれた世代に花田の遺産をどう継承していくかだが、残念ながら彼らの言説は必ずしも若い世代の心に届くとはいいがたいものだ。とはいえ、彼らの言説は、そこに花田の生き様が刻まれている点で、今日でもなおかけがえのない証言でありつづける。
花田の、黙殺・忘却のもうひとつの要因は、花田・吉本論争にある。吉本の罵声の声高さがあたかも勝利者の勝ち鬨の声のごとく響いてしまった論争以後、川本三郎がいうように「吉本から『ファシスト』という最大級の批判を浴びた花田」を読むことは、「ファシスト」に肩入れするようなものであったからだ。これが川本の個人的感想でないのは、かつて石崎等が、花田の仕事は吉本隆明の「鋭角的な問題提起と斬新な整理含んだ諸論文の水準に遠く及ばない」と断定したことでもわかる。(「花田清輝論」、『国文学・解釈と鑑賞』、七三年十一月)しかし、好村富士彦『真昼の決闘』(晶文社、八六年)は、そうした見解に根本的な修正を迫る。好村は、ドイツ文学者らしく吉本の戦争責任論をエルンスト・ブロッホに類比し、彼の「転向」論のキータームである「庶民」なる概念が「超時代的で不変なノッペラボーの化け物のように実体化」されているため、いきおい吉本の提起する、「庶民性」の克服から変革へむかう方向は、抽象的で図式的なものにならざるをえないことをあきらかにする。花田はその弱点をついたが、それに応酬した吉本の花田批判は、声高な罵声にすぎなかった。にもかかわらず、花田は敗者のように論争を退いていくが、その不可解な花田の行動を好村は奇抜に解釈する。花田は、演技として吉本に「負けてみせる」ポーズを取ることで、増長した吉本の自滅を待つ「意地悪じいさん」に徹したのだという。好村は、花田のテクストを彼が関わった運動と関連づけ、論争を前史や後史ともども正確に読み解くが、この書がユニークなのは花田と同様映画好きとおぼしき著者によってこの論争が表題どおり活劇仕立てで論じられているからだ。それゆえ、その結論は、いくばくかは遡及的な読みの危険を犯していて、研究というよりひとつの物語となっているが、その分スリリングな面白さがある。
久保覚が編集した『新日本文学』(一九八四年一二月号)には、彼でしか引き出しえなかった骨太な花田論がある。関曠野の「ナポリとオペラと泥棒論語」である。関は、花田を、イタリア旅行から帰ったゲーテにパラフレーズし、マルクス主義者ではなく、快活な唯物論者として見事に描き出している。花田はゲーテと同様「行為することで不断におのれを超出し他者と世界と歴史のさなかで自由になる唯物論的人間」にほかならなかった。花田は唯物論をもって「この国のおぞましい主情主義と便乗主義の風土、自らの感性によって思考することのできない知識人たちの書生根性」に反逆したのである。ここには、花田の唯物論を考察していくためのヒントがちりばめられている。