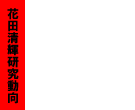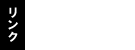花田清輝の研究動向3/4

だが、こうした花田の忘却への異議申し立ては、近代文学研究者からはほとんど提出されなかった。私の論文が掲載されるまで、長らく主要な学会誌には花田論ないし花田の作品論が発表されることはなかったし、大学の紀要においても『全集』完結後のおよそ二〇年の間に数編を発見できるだけである。私自身のの仕事『フェミニスト花田清輝』(武蔵野書房)および「光源としての唯物論的ユーモア」(『昭和文学研究』第三六集)については語る資格を持たないので、ここでは省略するが、そこでまずとりあげるべきは綾目広治の「花田清輝の弁証法」(ノートルダム清心女子大紀要第一三巻第一号国語・国文編、八九・三)である。これは、「対立物を、対立のまま、統一する」という花田の弁証法を正統的な弁証法との異同をあきらかにすることで、花田の変革の思想にまできりこんだ、アカデミズムのなかではじめて書かれた本格的な論文である。綾目によれば、花田の弁証法は、「事物は本質的に媒介されたもの」とする点では、ヘーゲル流の正統弁証法と深い交わりをもつが、正統弁証法とは異なり、統一よりは対立の契機が重視されている。綾目は、この対立物の葛藤への視座に花田の変革の思想の源泉をみ、久保が示唆していたバフチンとの共通性を論じながら、バフチン理論にはない、解体の後の秩序形成へのアプローチが花田の変革思想に包含されていることを見のがさない。花田は、現実、、の変革には、ただ破壊と転覆だけではなく、「組織する力」、秩序を形成する力を必須のものとみなしていたのだ。
最近綾目は「吉本隆明と花田清輝・論争の背後にあるもの」を書いたが、この論文は、吉本の「発想の骨組」がいかにスタティックで「近代主義」的なものにすぎないことを析出する。かつて吉本に心酔した研究者は、あらためて吉本のテクストばかりでなく、花田のテクストを読み直さねばならぬことをこの小論は教える。
渡邊史郎「表象される『花田清輝』・「ブリダンの驢馬」を巡る言説」(「稿本近代文学」第二〇集、九五・一一)、曽原祥隆「『自明の理』の周辺・戦前の花田清輝をめぐって」(「早稲田大学大学院教育学研究紀要別冊」九六・三)、中谷いずみ「回避するテクスト・花田清輝の『悲劇について』考」(『語文』九六・十二)は、いずれも二十代と推察される若手研究者の仕事である。この三者に共通しているのは、花田の初期のテクストにきちんと向きあっていることだ。渡邊は、読者論と注釈を結合する方法で「ブリダンの驢馬」を論じてきた論者が「何かを消去することで『花田清輝』」を表象してきたことをあきらかにする。曽原は、『自明の理』の「錯乱の論理」で花田は、マルクス主義の「反映論」ではなく、対象は認識によって構成されというカント的な認識論のあったがゆえにイデオロギーを「われわれの生にとって不可避なものであると捉ええた」と主張する。中谷は、花田の初期の小説「悲劇について」を、「AはAである」という同一性の形而上学、言葉の持つ固定化の性格を回避し、批判するテクストとして位置づける。
こうした若手研究者が黙殺されてきた花田に着目したことは、新鮮な驚きである。だが、彼-女らの論文を読んで起こる疑問は、なぜ花田なのかということである。つまり、黙殺されてきた花田を論じることが自分にとっていかなる意味があるのか、という問題意識が希薄なのである。あえて挑発的にいえば、マルクス主義者としての花田の変革の思想を脱色して、黙殺の状況に抗しえるのか、もしできるとしてはたしてそこにどれほどの意味があるのか、花田でなければならぬ必然はないのではないかと私には思える。三人は、政治的な問題をある程度留保できる初期のテクストではなく、花田が政治にまみれ、スターリニストの烙印をおされた五〇年代以降のテクストに挑むべきだと思う。