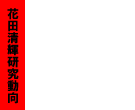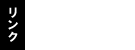花田清輝の研究動向4/4

黙殺の状況に抗し、なおかつ新しい展望をだそうとする試みのひとつの到達点は、石井伸男の『転形期における知識人の闘い方』(窓社、九六)である。この書が、花田のテクストを革命運動との関連におき(花田-吉本論争の再検証も含む)、そこに「知識人の闘い」を読みとろうとしているからだ。石井は、花田の根本的なモチーフが「近代を超えでること」にあるとし、とくに『復興期の精神』を高く評価する一方で、戦後の夥しいエッセイは「ボルテージの下がったそのコピー」であるとする。石井によれば、50〜60年代の花田のテクストが弛緩したのは、花田が「正統と異端」という枠組みを掲げ、たった一人でも正しい道を堂々と歩むものが正統派で、それを弾圧する権力こそ異端派であるとして、自ら正統派を主張し、マルクス主義の思想を守ることに汲々として、「個」を積極的に位置づけることができなかったためであった。花田の新たな転回は最晩年に書かれた『日本のルネッサンス人』である。石井はそこにサイード的知識人の、すなわち「知識人は弱者を代弁すべきである」と同時に「個人として自己を表明すべきだ」という「闘い方」をみる。花田が提唱した「共同制作論」は、個人と集団のそれぞれの独自性を両立させようという企図であった。
私は、石井のこの書を高く評価したいと思う。とくに彼は、花田の晩年の闘いをサイード的知識人にパラフレーズしてみせるが、サイードを引用しながら、決して弱者の代弁をしない、エリート主義的ポストモダニスト、ポストコロニアリストが横行しはじめている現在のアカデミズムでは、そうした花田を想起することに大きな意味がある。だが、石井の議論で承服できないのは、彼が六十年代の花田のテクスト、とりわけ小説を不当に無視していることである。私見によれば、花田の小説は「歴史」をパロディ化することで抑圧された人々の<伝統>を救出しようとする重要な試みで、この試みのうちに『日本のルネッサンス人』はすでにまどろんでいた。したがって、花田の最晩年に大きな転回があったというのは誤解である。とはいえ、そのことをのぞけば、石井の仕事がひとつの花田研究の到達であることは間違いなく、石井が欠落させた部分は、まさしく今後のわれわれの課題となろう。
われわれとは誰か?それは、自らの学問が、「弱い者、表象=代弁されない者たちと同じ側に立つ」ことにつながると同時にそこに「自分ならではの音声や、特別な語調や、さらには展望そのものを刻印」したいと考える者たちのことだ。そう考えるものが増えるとき、花田が忘却されるなどという驚くべき事態はありえないだろう。