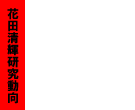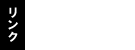『昭和文学研究』第36号 昭和文学会 1998年2月
「光源としての唯物論的ユーモア―尾崎翠と花田清輝
菅本康之
昭和は、小林秀雄の登場によって批評の時代となり、多くの傑出した批評家を生み出した。小林秀雄その人をはじめ、保田輿重郎、埴谷雄高、平野謙、花田清輝、吉本隆明、柄谷行人へと続く昭和の批評家群像。だが、1968年のパリの5月革命以後の「ポスト構造主義」の洗礼を受けたいまとなっては、その衝撃の後に実質的な批評活動をはじめた柄谷行人を除いた昭和の批評家たちの多くは色あせて見えるかもしれない。なにしろ、「ポスト構造主義」は、「人文科学」の「真理」の正統性に疑問を投げかけ、文化の「自律性」を否定し、「権力」と「知」の関係をラディカルに見直すことべきであることを唱えたのだから。昭和の批評家のほとんどは、「権力」や「政治」から「文学」や「芸術」の自律性を守ろうとしていたし、また彼らの多くは大学に雇われた大学人であった。現在日本のアカデミズム内部でも、ミシェル・フーコーの仕事に深く影響を受け、フーコー的「言説の政治学」に基づく研究が進行中だが、この立場からすれば批評家のディスクールはなんら特権的なものではない。それは、メディアや表象、様々なイデオロギーやディスクールのなかに位置づけられるものにすぎない。極端にいえば、小林秀雄のディスクールよりも新聞の大衆欄のディスクールの方が「権力」について真実を語っている場合もあるのである。
だが、そうしたフーコー的「言説の政治学」によって無化されるどころか、ある意味ではそれに対峙しうる「昭和批評」もある。それは、「文学」と「芸術」を擁護する昭和的批評家に対峙し続け、生涯アカデミズムの外部にいた花田清輝の批評である。
花田の衝撃的な独創性は、現在われわれに正当な評価を要求しているが、彼自身が自らの出自を語ることを禁欲的なまでに拒み続けたために残念ながらいまだにいくぶんか謎めいたところがある。同じマルクス主義者でありながら、中野重治との思想的な異質性は度を越しており、中野の思想と文体はむしろ花田の仇敵であった反マルクス主義者吉本と共鳴する部分が多いのである。花田が自分の出自をあきらかにしなかったのは、いうまでもなくウエットな「私小説」的批評の風土への唯物論的な立場から痛撃であった。だが皮肉なことに、そのことが花田の思想をどこかしら非唯物論的な謎めいたものにしているのであり、彼があたかも自分自身の子宮から自力で生まれでたかのような「オイディプス的な空想」を助長しているのである。彼が生涯その名にかけて闘い続けた唯物論の立場からいえば、むしろその独創性は唯物論的に説明されることではじめて意味あるものとなるはずである。つまり、われわれは彼の批評のスタンスと闘いのあり方にどこまでも敬意を払い、われわれ自身の場においても可能な限りそれを実行していかねばならないのだが、そのためにこそ彼の思想がいかなる歴史的条件において生まれたのかを問わねばならないのである。
花田清輝が、より正確には小杉雄二のペンネームをもって「文壇」に登場するのは、1931年5月のことであった。彼は『サンデー毎日』の「大衆文芸」寄稿募集に応じ、小説「七」
を書く。花田の「読書的自叙伝」によれば「プラーグの大学生のように、ひとりぽっちで、貧乏で、自分の影さえ手ばなさなければならないような境遇にあったわたしは、それらの書物のデータをつかって、一篇の読物をでっちあげ、前途を打開したいと考えたのである。」彼の小説は見事入選作となり、彼は、ほぼ一年間の自分の生活を保証する大金をまんまと手にすることになる。あまりの首尾良さに本人自身が驚き、「わたしはもう二度と、そんなくだらない物語を書こうとはおもわなかった。まさしくプラーグの学生と同様、わたしもまた、自分の影を悪魔に売りわたそうとしたような気がしたのだ
」という。
とはいえ、われわれは花田のこの回想を真に受ける必要はない。自分の過去を語ることに禁欲的であった花田ですらこの程度の回想は避けられなっかたのであるが、ベンヤミンが教えてくれたように過去は現在から絶えず、書き換えられており、この程度の回想にさえ重大な改変が忍び込んでいるかも知れないからである。はたして、花田は、「七」とは別にユニークなモチーフを持ちながらも、賞金稼ぎのために「七」を書いたのであろうか。それとも、「七」はまさに当時の花田の「文壇」的野心を担ったものではあったが、後年それを放棄した地点から「七」は否定されているのであろうか。今確実にいえることは、この「七」という小説から後年の花田を予想することは困難であるということだ。