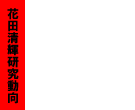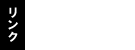「光源としての唯物論的ユーモア―尾崎翠と花田清輝2/10

「七」は、ボン大学元講師ペーテル・ペーターゼンなる人物が数字の七の神秘性に魅せられ、ついには彼の予感通り「七ツの力」導きによって命を落とすことになる顛末を、日本からドイツに留学し、ペーテルの親友となった「私」が語る小説である。「ペダンチックで該博な知識と洗練された文体」に、後の『復興期の精神』の萌芽を見るむきもあろうが、そこには「二つの世界」の対立がない点で決定的に異なっているのである。もちろん、「七」のなかにも観念の世界の住人ペーテルと俗物の権化であるシュルツの対決がある。だが、この対決は、観念が世俗的な権力に敗北するという、きわめて図式的なものにすぎないのである。7年後の「詩学
」(後の「悲劇について」の前半部の初稿)という小説には、生硬な形ではあるが「心理」と「論理」という対立が、一方が他方を敗北させるといった二項対立的なものではなく、葛藤し合いながらも互いに相手に浸透する「二つの世界」として、花田自身の言葉を借りれば「あの二つの世界ではなく、われわれの視線を、そういう上っ面の横の対立から、それよりもはるかに深みのある縦の対立に転ずることによって――すなわち、われわれが、『土の上』の横の対立ではなく、『土の上』と『土の下』との縦の対立をとらえるとき、はじめてわれわれによって、はっきりとその存在を自覚されるであろう二つの世界
」として追求されている。ところが、「七」にはそれがない。とすれば、平野栄久がいうように「花田が、『要するに、そこから、わたしは出発した』とするなら、否定するための出発でなければならなかった
」のである。実際花田はある友人への手紙に「書く方は止めた。断然止めてしまった。芸術とは何か、そういう事を考えている。乞食になった方がいいかも知れない」と書いているのだ。
およそ四年の空白の後、彼は花田清輝と小杉雄二として現れる。花田清輝は、中島誠のいう<表芸>をにない、小杉雄二は<裏芸>をになう 。<表芸>は「生計の足しにしていた」著述活動で、『東大陸』に掲載された一連の経済論や民族論を指し、<裏芸>は直接収入には関わらない執筆で、『東大陸』『文化組織』等に発表されたエッセイをいう。だが、この<裏芸>をになう小杉雄二はかつての小杉雄二ではなかった。ふたたびわれわれの前に現れた小杉雄二は、あきらかにわれわれの知る批評家花田清輝までもう一歩のところまで来ている。彼はいつしか弁証法的思考を手にいれ、「悲劇的」なものが「喜劇的」であるというパースペクティブを獲得しているのだ。たとえば、かつての小杉雄二が「傾倒」した小林秀雄に対して次のように辛辣に批判する。
懐疑、結構。逆説、悪くない。理屈抜きの邪念も――理屈ゆひの邪念にいたっては少々困り物だが、どうせ無力なものだから、まず認めてもいい。しかし、ただ一つ、どうしても譲歩できないのは、小林秀雄のあの鼻もちならぬメロドラマチックな調子である。感傷的な白である。チェホフの戯曲の一人物がいうように、「そのなかには、レトリックばかりたくさんあって、ロジックはまるでない。」(『伯父ワーニャ』)
何故彼は、彼の懐疑や逆説や邪念を、喜劇的に表現しないのだろうか。それは喜劇の対象以外の何物でもないではないか。