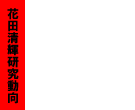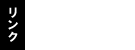「光源としての唯物論的ユーモア―尾崎翠と花田清輝3/10

この二年後、ここで彼自らが批判したレトリックを通して小林秀雄の対極の位置で闘いはじめる(「女の論理」)ところまではもう半歩のところであるが、とすれば、いきおい、空白の四年が問題にならざるを得ない。久保覚の労作である全集版「年譜」からわれわれが窺い知ることができるのは、花田は京都を引き払い、一時郷里の福岡に戻るが、生活に窮し東京に出る。ところが、東京では意に反していっそうの飢えを経験することになる、ということだ。この飢えのなかで彼は何とか食いつなぎながら、36年以後マルクス主義の文献を組織的に読むようになる。マルクス主義批評家花田清輝の形成はまさに、四年の空白の後に姿を現した花田清輝と小杉雄二の二つの名がやがて批評家花田清輝に合流していくプロセスをテクストに即して辿ればあきらかになるだろう。だが、それはここでの問題ではない。というのも、彼がどのようなマルクス主義者になるかは、それ以前の空白の四年によってある程度規定されているはずだからである。「年譜」にすでにありありと記されていながらも、これまであまり問題にされてこなかった事実。それは、ある小説との偶然にして必然的な、鮮烈にして持続的な出会いであった。
数字の七の神秘性に魅了された人物を描いた作者は、その七という数字の導きによってある奇妙な小説に出会う。人間にそなわっている五感ばかりでなく、芸術的直観に深く関わる六感さえも超える感覚世界である「第七官にひびくような詩を書きたい」と願っている少女<私>=小野町子が語る奇妙な物語。すなわち、尾崎翠の「第七官界彷徨」である。戦後の花田清輝の「ブラームスはお好き」というエッセイに尾崎翠の「第七官界彷徨」に触れた短い一節が登場する。
これは、ここだけのはなしですが、いまでもわたしは、ときどき、いっそひとおもいに、植物に変形してしまおうかと考えることがあります。そして、そんなとき、きまって私の記憶か底からよみがえってくるのは、尾崎翠『第七官界彷徨』という小説です。十代の終わりに読んだきりですが、そのなかに描かれていた苔の恋愛のくだりなどはすばらしくきれいでした。したがって、かの女は、相当、ながいあいだ、私のミューズでしたが、その後、風のたよりにきたところによると、気がくるってしまったということです。いま、手もとに本がないので読みかえしてみることのできないのが残念ですが、異常なまでにあかるい日のひかりのみちあふれたようなその小説なかには、みごとに植物のたましいがキャッチされていたような気がします。
本来はこのエッセイは安部公房論として書かれものであったが、そこに登場するこの一節は多くの人々を尾崎翠という、長らく忘却されていた作家へと誘った。あるところで「およそ物心ついてからずっと動植物に熱烈な関心を注ぎつづけていた私は、……花田氏がたたえる<二十世紀の植物のたましいがキャッチされている><異常なまでにあかるい>小説を、読んでみたいものだと思ったのでした
」と書いた加藤幸子は、『尾崎翠の感覚世界』という研究書の著者となる。今日でも最も優れた尾崎翠論のひとつといえる「歩行する蘚」のなかで山田稔は「書店の棚で『アップルパイの午後』という少女趣味的な表題の、……作品集を目にとめたとき、記憶の片すみに、……この作家の特異な世界に言及していた花田清輝氏の言葉がとどまっていなかったなら、はたして私はためらいを覚えつつも、あえてこの書物を購っていたであろうか
」と述懐している。「ブラームスはお好き」が発表された約8年後の1969年1月、遅まきながら花田と平野謙の推奨で「第七官界彷徨」は、學藝書林叢書「全集・現代文学の発見」の第六巻『黒いユーモア』に収録され、尾崎翠が最期の病で息を引き取る1971年には作品集『アップルパイの午後』が出版されたのであった。その意味で花田は、このエッセイの一節によって、ささやかな尾崎翠ルネッサンスの端緒をひらいた「最大の功労者」なのである。