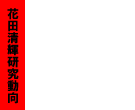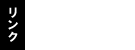「光源としての唯物論的ユーモア―尾崎翠と花田清輝7/10

こうしたグロテスクなリアリズムによってこのテクストのユーモアの根幹は支えられているわけだが、ここでの笑いがバフチンの笑いと同じであるなどというといいすぎになろう。尾崎翠の描くグロテスクなユーモアは、必ずしもバフチンの「グロテスクリアリズム」に由来する「カーニバルの笑い」に全面的に一致するわけではない。バフチンの「笑い」には、痛烈な因習打破、カーニバルにつきものの心地よい下品さと粗野な民衆性、そして底抜けの馬鹿騒ぎがあるが、このテクストにはそれらは決定的に欠けている。あるのはある意味では「カーニバルの笑い」とは対極にあるユーモアの笑いである。
フロイトによればユーモアとは「快楽を、それを妨害する圧迫的情動を無視して、獲得する手段である。それは、圧迫的情動の代替として機能し、その地位に割り込んでくる
」ものである。このテクストの笑いが底抜けに陽気にならないのは、たとえば、一助、二助、浩六によって町子は「女の子」としてしか認識されない状況、すなわち政治的な女性の解放が現実的には全く期待できない歴史の閉塞状況によるだろう。同時代の多くの「女流作家」あるいは「女性読者」は、恋愛を歴史の閉塞状況を越えるユートピア的なものとして構想したが、このテクストの作者尾崎翠にとってはそれは決してユートピア的なものではなく、むしろ限界を刻み込むものであった。とはいえこの限界とは川村が言うような作家の限界とそれから派生する作品の限界とは異なる。
柄谷行人はフロイトとボードレールに依拠しながら「ヒューモア」を「有限な人間の条件を超越することであると同時に、そのことの不可能性を告知するためのもの」であると定義している。いわばそれは「自己の二重化」であり、「『同時に自己であり他者でありうる力の存することを示す』(ボドレール)ものである。
」柄谷とって唯物論とは、有限な人間の条件を超出しながら、同時にそのことの不可能性を告知することであり、「自分は世界(歴史)のなかにあって、それを越えることはできず、越えるという思いこみさえもそれによって規定されているという、超越論的な批判」である。そして、それこそが「ヒューモア」でもある。こうした唯物論の理解の仕方こそ、花田清輝につなげなければならないものだが、この柄谷の議論から影響を受けたと思われる生方智子の卓抜な指摘によれば、「第七官界彷徨」の語りの構造はまさしくそうしたユーモアによって起動する。
物語の終わりで第七官の詩を書くことのできない<私>は、物語の始まりで物語を語る<私>となっているのである。<私>に関してテクストの冒頭と最終部では大きな飛躍がある。……テクストの冒頭で「よほど遠い過去のこと」と物語を回想して語る<私>は、第七官を彷徨する<私>には到達できなかった場所に立っている。それは「私自身」をみつけることのできない<私>を、ユーモアを持って語る<私>という場所である。ユーモアこそ、語られる<私>から語る<私>への飛躍の機動力なのである。
ここまでくれば、「第七官界彷徨」との出会いが花田にとっていかに衝撃的なものであったかが、理解できるだろう。モンタージュや対位法によってもたらされる対立するものの複合、映画のクローズアップの技法の導入、遍在する唯物論的イメージ、そして唯物論的なユーモア。尾崎翠を読んでいない花田読者は、「第七官界彷徨」に花田思想の先取りを見て驚くことだろう。花田は、尾崎翠を「永遠のミューズ」と呼んだが、これは決して誇張ではなく、まさしく「第七官界彷徨」は彼にとって光源でありつづけた。ただ彼はできることならそれをつまびらかにしたくはなかったのだ。なぜなら、花田清輝は過去を絶縁してきた批評家でなければならなかったからである。最晩年の次のようなエッセイにはそうした事情が率直に記されている。