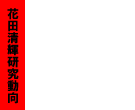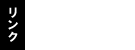「光源としての唯物論的ユーモア―尾崎翠と花田清輝8/10

テレビでは、好んでご対面を見る。突然、過去が出現すると、人間というものは、困惑したり、あわてたり、涙をながしたり−−要するに、日ごろは、とりすましてひたかくしに、かくしている自らの正体を、おもわずバクロしてしまうものらしいのだ。<中略>
十年ばかり前、わたしは、尾崎翠の『第七官界彷徨』について、「十代の終わりに読んだきりですが、……みごとに植物のたましいがキャッチされていたような気がします。」とかいた。そして、それから数年後、わたしは、四、五人の文学者たちと一緒に、昭和文学のアンソロジーの編集をすることになった。すると、編集会議の席上で、久保覚が、「これを、おいれになりますか。」といって、わたしにむかって、『第七官界彷徨』の初版本を手渡した。<中略>
何十年目かの不意のご対面に、わたしはあわてた。そして「昔読んだきりだから、もう一度、読みかえしてみなければ。」とためらった。「でも、ちょっとそんじょそこらにころがっている作品とはちがうような気がするけどなア。」と、久保覚は、ひどく自らの掘り出し物にみれんがあるらしかった。そのとき、平野謙が、きっぱりと、「尾崎翠はいいです。いれましょう。」と結論をくだした。そこで、その作品は、そくざにアンソロジーにいれられた
。
このエッセイで花田は自らの隠蔽を率直に認めているが、それは晩年の彼をなお狼狽えさせうるものであったことはたしかである。しかし、われわれの目的は花田の隠蔽を暴露し、それを非難することにあるのではない。隠蔽を解くことによって特異な批評家として異端視された花田が歴史にしめている位置をもう一度あらためて見直してみようということにほかならなかった。
ファシズムの岸辺に打ち上げられた彼が、歴史にあらがいながら、マルクス主義革命運動の壊滅語にマルクス主義者になったのは「第七官界彷徨」がきっかけではない。尾崎はマルクス主義者ではなかったし、「第七官界彷徨」は政治的なテクストではない。にもかかわらず、マルクス主義批評家花田清輝を可能にしたのは尾崎翠であるといえる。というのも、彼が日本のマルクス主義の歴史にしめる独創性は、「七」執筆当時に傾倒していた小林秀雄のテクストからも、36年頃から組織的に彼が読んだであろうマルクス主義の文献からも説明できないからである。私はあるところで花田清輝の独創性が、唯物論に対する革命的理解、歴史観の革新、フェミニズムとの対話の三点にあることを示唆した
が、尾崎翠の「第七巻界彷徨」から花田が学んだものは、唯物論の革命的理解につながる唯物論的ユーモアであった。
T・イーグルトンによれば、「『ユーモア』というのはマルクス主義にはほとんど馴染みにない概念である。 」事実、P・アンダーソンが分析した20世紀の、ルカーチからアルチュセールにいたる「西欧マルクス主義者」のテクストのなかで「ユーモア」がマルクス主義の闘争の主要な戦略として登場することはない。繰り返し登場するのは「悲哀」や「メランコリー」であるが、それらはプロレタリアート階級の敗北の歴史を淵源としている
。花田が批評家として出発しようとしている時期において日本のプロレタリアート階級の敗北の状況は悲惨の極みであり、その意味で彼のテクストに狡猾に「悲哀」や「メランコリー」が忍び込んでいたとしてもなんの不思議もない。ところが、実際にはそれらを見つけだすことはむずかしい。だが、考えてみればこのことはさほど奇妙なこととはいえまい。史的唯物論にしたがえば、プロレタリアート階級の歴史的な敗北が「西欧マルクス主義者」に「メランコリー」を発生させるのは当然のこととしても、見方をかえればそこに「ユーモア」をみることもできる。というのも、ユーモアとは、ズレから生じるものであるからだ。死刑台にゆく死刑囚が、最期の煙草の施しを断るのは、禁煙していたたためであったという話やエッフェル塔嫌いの男が毎日エッフェル塔のなかのレストランで食事をとるのは、そこが唯一パリでエッフェル塔の全貌が見えない場所だからだという話にわれわれが笑うのは、死刑囚や男が置かれている状況と彼らの反応との間のズレをみいだすからである。とすれば、プロレタリアート階級の勝利が必然であるはずなのに、革命運動が本格的にはじまりもしないうちに壊滅してしまうとは、ユーモアに値する、何と壮大なズレであろうか。マルクス主義革命運動の壊滅の後にマルクス主義者になる花田の前にはそうしたズレがあったのであり、彼はその状況をユーモアをもって受け入れたのである
。もちろん、誰もがそうした状況を「ユーモア」で解するとはかぎらないだろう 。だが、花田の場合は尾崎翠のテクストによって「悲劇」から「喜劇」を引き出す方法を学んでいたのである。暗澹たるファシズムの時代のなかで、尾崎のテクストが一つの光源として照らし出した唯物論的ユーモアの道を花田は歩み、そしてマルクス主義に出会ったのだ。