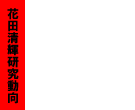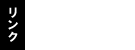マニフェスト 2/3
ベンヤミンは、「過去」を確定してしまったもの、完結してしまったものとは見做さない。むしろ、「過去」とは、この現在と連動し、つねに「現在」のわれわれにふりかかってくる何ものか、なのである。ベンヤミンにとって「過去」を「固定的な点と見做」すような「歴史観」は、均質な時間が流れる支配者階級の時間すぎないが、ベンヤミンが救済しようとした「過去」=「伝統」は、抑圧され搾取されたものの方に属している。この抑圧され搾取されたものの<伝統>を「想起」し、その苦悶の声、憎悪、犠牲への意志を、そして何よりも彼―女らの「夢」を「現在」において覚醒させること、それがベンヤミンのいう「史的唯物論」、すなわち「歴史観」におけるコペルニクス的転換であった。
花田清輝もまた、マルクス主義者でありながら決して「唯物史観」=「進歩史観」には、与しなかった。ファシズムの岸辺に打ち上げられた花田は、自らの思想的な出発において否応なくファシズムとの関係を運命づけられたが、彼はその「歴史」にあらがいながら、日本のマルクス主義革命運動の壊滅の後にマルクス主義者になった。「戦時下」において書かれ、「戦後」出版された『復興期の精神』の「終末観--ポー--」において次のようにいう。
…死とはいっぱんに考えられているほど、それほど不毛な観念ではない。…まこと に意外なことに、究極の言葉は、たちまち発端の言葉に転化する。万事が終わったと思った瞬間、新しく万事が始まる。すなわち、飛沫をあげ、流れにしたがって下るのではなく、その流れの死に絶えたところ--水勢ゆるやかな河口から、かれは悠々と溯りはじめる。河口の向こうには、果てもなく、虚無が海のようにひろがっている。そうして、そこからながれこんでくる潮流が、大いに彼の航行を助ける。……なるほど、死の観念が、きわめて生産的であり、組織的であるということは、一見、逆説めいており、不自然な感じをあたえるかもしれない。腐爛し、崩壊し、消滅するものが死だ。だが、それ故にこそ、人は死の観念に附き纏われることによって、きわめて生産的にもなるのではないか。……どん詰りからの反撃は、それほど困難ではない。死の記憶が、絶えず、我々を驀進させ、死の想像がつねに我々を組織的に一定の軌道のうちに保つ。
あるいは、「晩年の思想-ソフォクレス」において、「朝、昼、晩の三拍子をとって進」もうとするブルジョア唯物論を嘲笑う。
…いきなり晩年から出発するのが、ルネッサンス的人間の克服の上にたつ、我々すべての運命であり、一気に物々しく年をとってしまうのは、なにもラディゲのような「天才」ばかりのたどる道ではあるまい。したがってまた我々は、消え去る青春の足音の木魂するのをききながら、『退屈な話し』の老人ように、しずかに頭をふることもないのだ。……オイディプスの晩年からはじめるということは、むしろ、そういう植物や、動物のような状態から我々の脱出によって可能であり、人間の生長や、闘争や、歴史的発展などにたいする生物学的解釈への訣別を意味する。一言にしていえば、それはエヴォリューションとレボリューションとの区別の上に立つということだ。
…ルネッサンス的人間の自己否定は敗北ではなく、我々は、かれらの落莫とした晩年を、身にしみて感じないわけにはいかないのだ。喝采を放棄し、尾羽打ち枯らさなくて、なにができるか。われわれの欲するものは栄光ではなく、屈辱なのだ。闘争にとって不可欠なものは、冷酷な晩年の智慧であり、一般に想像されているように奔騰する青春の動物的エネルギーではない。
このように、「死」と「晩年」から逆転して回生に向かう花田の「晩年の智慧」、あるいは「結末」から発端に向かう「逆行」の思想は、「唯物史観」とは、全く異質なものである。