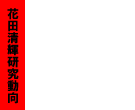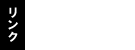マニフェスト 3/3
しかし、花田清輝の思想にとって「不幸」なことは、彼がベンヤミンとは違って「大戦後」も生き、「社会主義国」の幻想になにがしか加担してしまったことである。1950年代の花田のテクストには、「社会主義リアリズム」と「アヴァンギャルド」を弁証法的に統一しようとする、花田自身のことばでいえば「対立を対立のまま統一する」という、かつてロシア・アヴァンギャルドが、30年代前半においてベンヤミンがみた「夢」を、スターリニズムを擁護するかたちで表明してしまっているきわどさがある。花田が「夢」を織りなしていた頃、ソ連邦共産党大会でのフルシチョフの秘密報告によるスターリン時代の驚くべき事実の暴露(56年)、ポーランドのポズナニの反政府暴動、ハンガリー動乱、日本においては火炎ビン闘争といった「極左冒険主義」革命運動の「大衆」からの決定的な遊離が起きていたのである。「社会主義」幻想の瓦解という「歴史」の試練は、あきらかに花田のテクストからベンヤミンのテクストがもっているようなアウラを剥ぎ取ってしまっている。その意味で、あの花田?吉本論争における「敗北」は、花田が吉本隆明の思想に屈したのではなく、むしろ、自らの「社会主義」幻想に対する根底的な自己省察と自己批判を意味しているのである。
それでもなお、われわれが花田清輝のルネッサンスを企てるのは、彼が「社会主義」幻想の廃墟から、ときに強靱に、ときにしたたかに、そしてときに荒唐無稽に「革命」の可能性を垣間見せてくれるからである。58年の『泥棒論語』以降の、「歴史小説」、「戯曲」において、花田は、「歴史」を、彼自身の造語でいえば<転形期>--あらゆるものが流動し、変転を起こして姿を変えようとしている時期、抑圧されていたものが目覚め、新たな存在に生まれ変わろうとする時--を「パロディ化」することで「歴史」の連続性を打破し、抑圧されたひとびとの<伝統>を「確信や勇気やユーモアや知慧や不屈さ
」(ベンヤミン)として救済する。
驚くべきことに、日本の「文壇」ジャーナリズムおよびアカデミズムは、そうした花田の仕事を徹底的に「黙殺」してきた。あるいは、「倫理なき資本主義」において、「流行」それ自体が<物心崇拝>の対象となってしまう現代の日本の状況において、それはむしろ当然な帰結といえるだろう。だが、まさに「黙殺」され「忘却」されているそのマイナー性ゆえにこそ花田清輝のテクストは、「世界資本主義」の根源的な批判、あるいは「転覆」の力となりうるのである。「前近代を否定的媒介にして近代を超える」という花田清輝のテーゼは、いまなお「覚醒」のときをまっている。