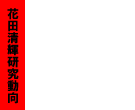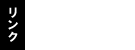『国文学解釈と鑑賞』別冊『坂口安吾と日本文化』 至文堂 1999年7月
「花田清輝―唯物論の復権」
菅本康之
坂口安吾と花田清輝との交通、そもそもそれは、それぞれの仕事の背後に隠れたものだったが、アカデミズムをも腐食するポストモダニズムのすさまじいインフレーションの中では、いっそう色褪せたものに思えるかもしれない。しかし、それが狭い領域に秘められているまさにそのことによって、表舞台でおこなわれている過剰な言説の闘争の意味を足下から照らしだす光源ともなりうるだろう。
坂口安吾は、「花田清輝論」で花田を絶賛するが、このエッセイは、無名の左翼批評家をいち早く発見したものとして記憶されている。安吾はそのなかで、花田の思想が、「その誠実な生き方に裏書きされている」こと、「思想自体を生きている作家精神の位」の高さを強調する。その後安吾はほとんど花田について書くことはなかった。また、安吾と花田が直接顔を合わせたのはたった二度にすぎない。このことは、一見、『復興期の精神』は認めても、戦後の花田の仕事は否認するといった、よくある凡庸な花田評価に、安吾も与していたように思わせるが、安吾にとって花田は、政治的信条を異しながらも、ともに闘うべき相手であって、闘争の相手(たとえば小林秀雄)ではなかったのだから、ただ花田の闘いを見守りつづければよかったのである。事実、安吾は『新日本文学』の仕事で桐生の彼の自宅に訪れた花田にむかってしごく真面目に「モグるようなことがあったら、ぜひぼくのところへいらっしゃい、ぼくは捕物帖をかいているし、そんなことをするのが大好きだから」といったという。
花田清輝は、安吾が共闘すべき存在であることをより強く意識していた。あるエッセイのなかで花田は、安吾を、グァレスキの小説の人物ドン・カミロ(カトリックの坊主)に、自分をその敵のペポネ(共産党員の村長)の一味にたとえているが、イデオロギー上では執拗に対立しつづけるカミロとペポネの二人の友情は、レジスタンスの伝統に立ったところに存在していたのだった。それゆえ、ペポネの一味を自認する花田は生前の安吾を絶賛することはなかった。花田の最も長い安吾論、「動物・植物・鉱物」では、安吾を「とがれる口長く、垂れ耳大きなる」猪=猪八戒にたとえ、彼の芸術家としての不徹底ぶりを、辛辣に批判している。すなわち、安吾の芸術即生活、「描きながら生きたい」という信条は、垂れ耳=肉体・生活ととがれる長き口=魂・芸術の分裂を「行」によって解決をはかろうとする形而上学にほかならず、「赤裸にされた魂と肉体をながめ、もし両者が分裂しているなら、真向から肯定すべき」であり、そこにしか「坂口のいわゆるファルス(滑稽)の世界」は展開しない、と。花田にとって、安吾の「初期のファルスめいた作品」は、「魂と肉体との分裂を正視することができず、一応、肉体を動物ととらえたにせよ、それに魂を同伴させることを拒絶した」ものにすぎない。たしかに『吹雪物語』からは魂と肉体の分裂に真正面から取り組んでいるにしても、「その分裂の事実は、…ファルスどころか、おそろしく悲劇的なもの」でしかない。『木枯の酒倉から』や『風博士』以降、安吾の作品には、「かれの魂と肉体との分裂にたいする慟哭や自嘲や絶望によって充たされており、したがってまた、…揺るぎのない知行一致の境地に対する憧憬のはげしくながれているのをみとめ得る」が、「その憧憬が、彼の作品を、至極、感傷的なものにして」いるのである。