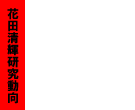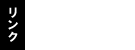「花田清輝―唯物論の復権」2/3

魂と肉体は、決して分裂しておらず、いずれも「言説」において構築されるものにすぎない、などと考える浅薄な「言説主義者」のために、花田の議論を擁護すれば、彼のいう「魂と肉体の分裂」の肯定とは、唯物論の肯定にほかならないのである。われわれは、まず自分の精神が自分の肉体に宿っていることに違和を感じ(たとえば、自殺を真剣に考えているのに空腹を感じるように)、やがては世界のあり方や表象そのものに異和を抱く。唯物論者は、その異和ないし矛盾を冷徹に直視し、表象を超える物質なるものにむかっておこなわれる限りない接近の実践運動を通して、自分を囚えている言説や表象をたえず打ち破りつづけようとするのである。ファルスとは、その時、言説や表象の裂け目からやってくる物質や「実在」のノンモラル、ノンセンスにふれたときに沸き起こるものにほかならない。花田の安吾への批判は、まさしく彼の唯物論の不徹底を咎めるものだった。
花田は唯物論の立場に立つ批評家であったが、たしかに安吾もまた、唯物論的作家であった。それは、彼のエッセイ「FARCEについて」や「文学のふるさと」に如実にあらわれている。「ファルス」を「本当の意味無しナンセンス」に、「凡有あらゆる物の混沌の、凡有あらゆる物の矛盾の、それら全ての最頂点パラロキシミテに」見、「モラルがないこと」、自らを「突き放す」ものに「文学のふるさと」を感じる安吾の感覚は、唯物論者特有の感覚である。表象をはみ出した物に出会うことによって感じる異和、意識を超えた「実在」との出会いから生じるノンセンス、ノンモラルから出立する安吾は、期せずして?意味は先行しない?という唯物論の起源であるエピクロスのテーゼを敢行していた。エピクロスによれば、世界形成以前には無数の原子アトムが真空のなかを落下していた。そこには、形式を与えられたものはまったく存在せず、あらゆる要素は、永遠に、孤立してすでに実在していた。この落下する原子アトムのイメージは、安吾の「堕落論」の「生きよ墜ちよ」という言葉にこそふさわしい。だが、もし川村湊がいうように、この言葉の「"生きよ"というということに重点があって、"墜ちよ"ということにではない」ならば、そこには花田のいう「魂と肉体の分裂」の肯定の不充分さがあるといえる。なぜなら、落ち=墜ちつづける原子アトムがもつ小さな偏向クリナーメンがだけが他の原子アトムとの出会いを誘発し、この出会いこそが原子アトムに現実性を与えるだから。生きるというモラルに重点をおいた瞬間、そこには生ぬるい生の感覚(上昇意識や絶望や感傷)が侵食し、ノンセンスやノンモラル、あるいは表象を超えた「実在」は遠ざかる。
「動物・植物・鉱物」を書いた前後の一時期、花田は集中的に、唯物論を押し進めているが、それは、彼のエッセイ「物体主義」や「ドン・ファン論」、「マザー・グース・メロディー」にみることができる。とくに「マザー・グース・メロディー」では、ノンセンスを「ボン・サンスの拘束を超越している状態」、「極度の理知も、その前に立つと、たちまち眩暈をおぼえはじめるような、物それ自体のすがたを示す、…外部の現実」であると定義する。「ナンセンス」は、「人間」にとっていつまでもスキャンダラスな物質の「因果律」?物質の重層的・非線的なネットワークなのである。したがって、この「ナンセンス」にむかいあうとき「眩暈」をおぼえるのは、われわれの「生」が物質の生成と衰退の過程である以外、いかなる根拠ももっていないことを知らしめるからだ。このナンセンスからの転回は、不断の行為=実践を通じて他者と世界と歴史のなかでおのれの「主体」を確立していくしかない。絶えず外部の物質的現実に向かいながら、おのれを物体の状態にまで追いつめ、自らの非人間性をはっきり自覚するときはじめて「主体性」は確立する。マルクスにとってそうであったように、花田においても唯物論とは、新しい主体の創造をめざすものであった。(ここが「主体」を忌避し、代理表象しないことを金科玉条にする軽薄なポストモダニストとの決定的な違いである。)もちろん、花田のいう「主体」は固定された統一体でない。原子アトムが偏向クリナーメンによって偶然の出会いを繰り返していくように、この「主体」は物へ向かう運動によって絶えず、そのフォルムを変えていく。「砂」が、「砂漠」で無限の創造運動をおこないつづけるがごとく。したがって、「肉体と魂の分裂」の前でただおろおろしつづける感傷的な坊主には、痛棒をしたたかくらわせねばならぬ。それが、レジスタンスによって結ばれたものの友情の証である