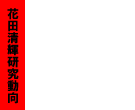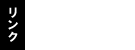「花田清輝―唯物論の復権」3/3

だが、共産主義者花田が、世界の政治的状況に愚弄されている間に安吾は、まんまと彼を出し抜いていたともいえる。花田は、安吾の死に際し、彼なりの弔意をあらわそうと、それまで読んだいなかった『安吾捕物帖』を読むことで安吾をしのぼうとする。そのとき彼は、自分が安吾によって見事に出し抜かれていたことに気づき、安吾が「精魂かたむけて捕物帖をかいているとは知らずに、安吾論をかいたりしていたことに舌をかむおもいを味」わうことになる。
花田は「安吾と捕物帖」で「ここにはチェスタートン風のモラリストらしい観察やユーモアがあるばかりでなく、奔放な想像力や豊富な歴史的知識を駆使してとらえた幕末から明治へかけてのわが国の転形期のなまなましいすがたがある」と評価し、「捕物帖を愛するゆえん」では、「『安吾捕物帖』のネライは、日本の伝統との対決にあるのだ。…『安吾捕物帖』こそ、芸術の大衆化に成功した、最初のモニュメンタルな作品である」と絶賛する。唯物論者花田をしてかようにいわしめる核心は、それまでの安吾作品につきまとっていた「おそるべきノスタルジア」をふきとばす「ドキメンタリー・タッチ」と「いまだにわれわれの身辺に生きつづけている前近代的なものに肉迫し、仮借することなく、その病根をえぐりだ」す、安吾の「あざやかな執刀ぶり」にあった。花田はそこに「転形期のプロレタリアートの生態」が「いきいきと、とらえられている」のを認めないわけにはいかなかった。こうした花田の安吾評価は、必ずしも分析的なものではなく、批評的直観というべきものにすぎなかったが、関井光男がいうように、「安吾捕物帖」にそうした卓越した評価をなしえたのは花田清輝ただひとりだったのである。
この後花田はまとまった安吾論を書くことはなかった。だが、見方を変えれば、安吾没後の花田の仕事の大半は安吾がきりひらいた可能性へのオマージュであるともいえる。というのは、戯曲『泥棒論語』(一九五八年)以後の花田の仕事の主眼は、「伝統」との対決と抑圧されているもうひとつの?伝統?の救出にあったからだ。「土佐日記」や「平家物語」をはじめとする様々な転形期のテクストを差異をもって反復し、繰り返すこと、つまりはパロディ化することで、歴史の連続性を打破し、抑圧されたひとびとの?伝統?を「確信や勇気やユーモアや知慧や不屈さ
」(ベンヤミン)として救済しようとする。?転形期?とは、?状況?そのものであり、あらゆるものが流動し、変転を起こして姿をかえようとしている時期、それは抑圧されていたものが目覚め、新たな存在に生まれ変わろうとするときでもあるが、花田はこの?伝統?=?転形期?を救出することで、今ある「歴史」や「伝統」とはちがった可能性がありうることをわれわれに示そうとした。それは、「伝統」との対決を通して個人主義者坂口安吾がなしとげた「モニュメンタル」な仕事に対する共産主義者としての応答であった。安吾が、「『禀質』という言葉でいうのが適当のような、魂の美しさと才能」をもった「エクサイル」、すなわち「社会から追放された『反抗的人間』」なら、花田は、?転形期?に「個人主義の限界を突破しようとする、あたらしいうごき」をみいだし、「伝統」を変革することにこだわる、愚直で喜劇的な「革命的人間」なのであった。
おそらく、「捕物帖にくらべてみると、…『白痴』も『火』も『信長』もことごとく、児戯に類する」とする、花田の安吾評価は、偏向している。だが、原子アトムがもつ偏向クリナーメンが世界をつくるように、花田の偏向は、安吾のテクストとの刺激的な出会いを生みだすばかりでなく、われわれに花田のテクストとの新たな出会いをも用意する。二人の「友情の政治学」がもたらすもの、それは唯物論の復権にほかならない。